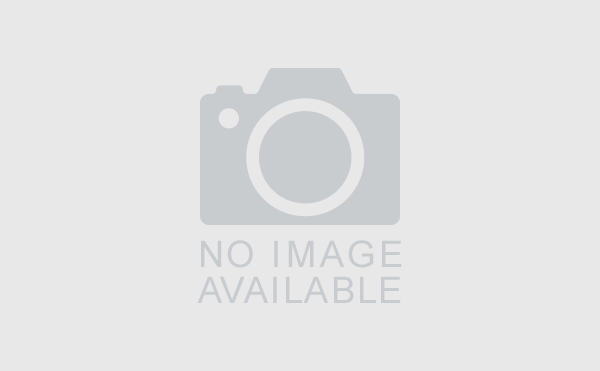70代以上の人、薬を減らそうよ‼
「70代で持病があり薬を飲んでいる人がどのくらいいるか」というのは、公的な調査がいくつかあります。
1. 厚生労働省「国民生活基礎調査」(2022年)
- 70代で「現在何らかの病気で通院している」人は 男性で約70%、女性で約80%。
→ 7割以上が「持病あり」と答えています。
2. 処方薬の服用状況
- 厚労省や医療経済研究機構の調査によると、
70代の約80%が定期的に薬を服用しています。 - 特に多いのは
- 高血圧薬
- 脂質異常症(コレステロール)薬
- 糖尿病薬
- 心臓や血管系の薬
などです。
3. 薬の数
- 70代の服薬数は平均で 4〜5剤前後 と言われています。
- 5種類以上を飲んでいる人(多剤服用、ポリファーマシー)は 40%以上。
✅ まとめると
70代の約7〜8割が持病を抱え、何らかの薬を日常的に飲んでいる、というのが実態です。
図で示すと下記のようになります。
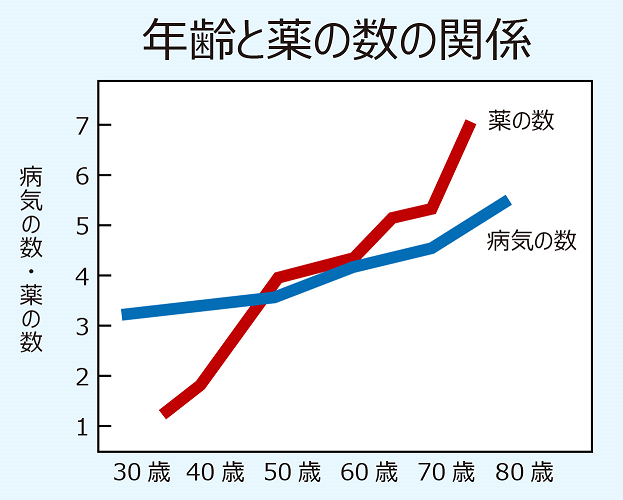
薬が増えるのは仕方がないことか?
① 「年齢とともに薬が増える」のはある程度自然
- 70代になると、高血圧・脂質異常・糖尿病・前立腺肥大・呼吸器疾患など、いくつかの慢性疾患が重なりやすく、薬の数が増えやすいのは事実です。
- 特に「血圧の薬」は、腎臓や脳・心臓を守るための予防薬として位置づけられているので、投薬自体は妥当と考えられます。
② ただし「薬が増えるのは必ずしも避けられない」わけではない
- 不要な薬を整理して、最小限で済ませることは可能です。
- 例えば:
- 同じ効果の薬をまとめる(一剤に切り替える)
- 症状が安定している薬を減らす(前立腺薬やアレルギー薬など)
- 一つの薬で複数の効果があるものを選ぶ(例:ARBで血圧+腎臓保護)
実際の工夫
- 主治医に「ポリファーマシー対策」を相談
→ 「血圧薬を追加すると薬が増えますが、他に減らせる薬はありますか?」と聞く - 症状がない薬の見直し
→ 前立腺やアレルギー薬は「症状がなければ減量や中止」が検討できる - 配合剤の活用
→ 例えば「血圧薬+利尿薬」が1錠に入った薬などもあり、錠数を減らせます
ポリファーマシーとは?
- 本来は「多剤併用」という意味ですが、
- 医療の現場では 必要以上に多くの薬を飲んでいる状態、
あるいは 薬の飲み合わせや副作用でかえって健康に悪影響が出ている状態 を指します。
ポリファーマシーで起こりやすい問題
- 副作用のリスク増加(ふらつき、腎機能悪化、肝障害など)
- 飲み合わせの悪影響(一方の薬がもう一方の効果を弱めたり強めたりする)
- 飲み忘れ・飲み間違い(錠数が増えると管理が難しい)
- 医療費の負担増

ポリファーマシー対策でやること
- 薬の総点検
- 今飲んでいる薬をすべて(処方薬、市販薬、サプリも含めて)リスト化
- 医師や薬剤師が「まだ必要か?重複していないか?」を確認
- 優先順位をつける
- 命を守る薬(血圧・糖尿病・心臓・腎臓) → 優先的に継続
- 症状が軽い時に使う薬(胃薬、アレルギー薬など) → 状況を見て中止可能
- 飲み合わせのチェック
- 腎臓や肝臓に負担をかける薬が重なっていないか
- 同じ作用の薬を二重に使っていないか
- 処方の簡素化
- 1日2回→1回にできないか
- 配合剤(2種類が1錠にまとまった薬)を利用できないか
- 定期的な見直し
- 年に1〜2回は「この薬、まだ必要ですか?」と主治医に確認
以上、自分の身体ですので、お医者さんにかかるとき、薬についても尋ねてみるのも大切なことだと思います。